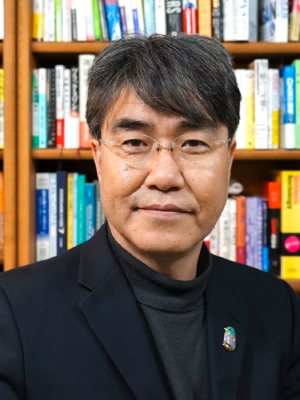
東北大学大学院歯学研究科長
小坂 健
2020年、東北大学大学院歯学研究科は、東北大学大学院農学研究科および宮城大学食産業学群と連携し、世界初の学際共創科学として「食学(Shoku-gaku)」を創生しました。「食学」という言葉は聞きなれないと思いますが、これは、食べ物の入り口である口腔の科学、すなわち「歯学」と、これまでの“食”の科学である「食品科学」と「栄養科学」を統合・融合した世界初の学問です。その活動拠点として「革新的食学拠点」を設置しました。
健康の“みなもと”は「食べること」です。超高齢化の進む日本、とくに高齢化が著しい地域が東北地方であることを考えた時、東北の地で、“食”に関する新しい学問が誕生することは、大変意義のあることと思います。一方、世界に目を転ずれば、今後、先進諸国を中心に高齢化が進むことは避けがたく、 “食”の問題は大きくなることでしょう。これはすべからく、SDGsの項目として掲げられていることでもあります。「食学」は、世界に先駆けてこれらの課題を先取りし、解決を図ろうというものであり、その役割はこれから益々重要になると考えます。
歯学研究科は、2002年に「インターフェイス口腔健康科学(Interface Oral Health Science)の概念を創出し、「口の再定義」を行いました。この20年、歯学の役割は口腔疾患の予防・治療から口腔と全身の健康増進へとその役割が大きく拡大してきました。健康を考える上で“食”はもっとも重要であり、口の学問である歯学は、健康増進の担い手として“食”の学問を行う責務があると考えます。ある意味、「食学」は、健康増進を目指すこれからの歯学の再定義の一つとも言えるのです。
「食学」は、医療・保健・福祉において、治療から予防・未病対策そして健康増進、幸福増進へとシフトさせ、今後、人類が直面する超高齢社会の持続的活性化を目指します。-いつでもどこでも(超高齢でも災害時でも)、おいしいものをおいしく食べて、生涯にわたり健康で幸福な生活を送る- これを実現するため、「食学」では、最先端の研究成果を社会へ還元する「社会との共創」を推進します。「食学」は、社会に実装され、社会で実証されてこそ、意義あるものになると考えるからです。多くの皆様のご理解とご支援、そしてご参加を、門戸を広く開けて、心よりお待ちしています。

